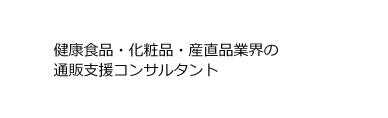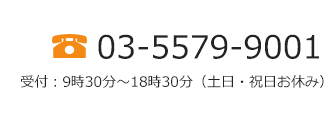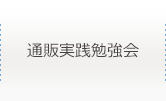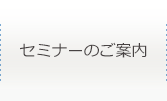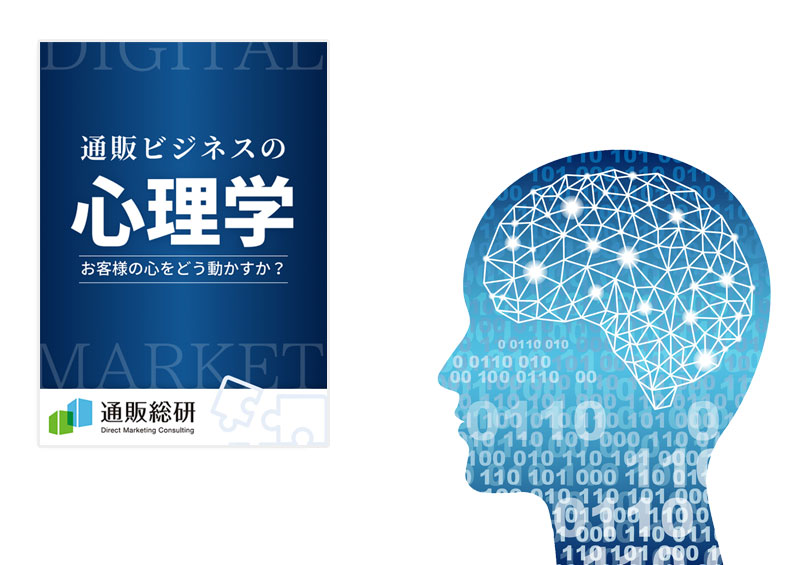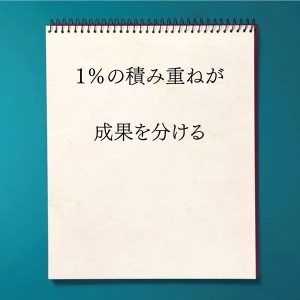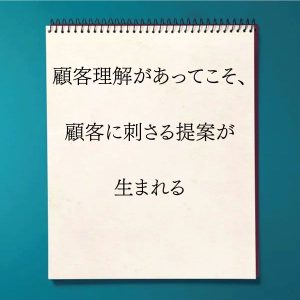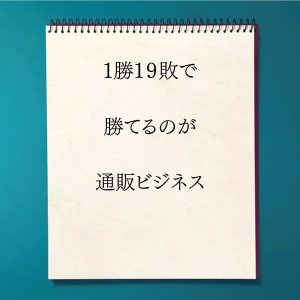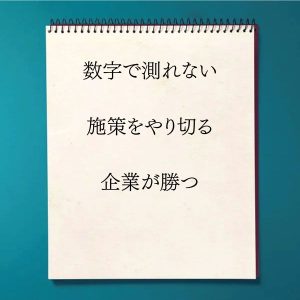広報としてのSNSの活用
SNSの活用は通販会社にとっても重要なテーマですが、活用にあたっては目的を明確にすることが大切です。いざ投稿を始めたはいいが、手間の割に成果がわからず、自社の社員や知り合いしか「いいね」を押してくれない。そんな状態が続くと、投稿のモチベーションも上がらず施策としても続かなくなってしまいます。
SNSは投稿したら、すぐにバズって売上アップなんてことはありません。そんな中、会社や商品の認知度を上げる広報としての役割を目的にSNSを活用する企業が増えてきました。
面白くないと誰も見ない
一般の人にとっては、ある企業の投稿を見に行く必然性はありません。やはりコンテンツとして面白いかどうかがポイントになります。そんな中、情報発信に成功している事例を2つ紹介します。
有隣堂書店は、創業114年を迎える老舗書店ですが、Youtubeの発信に力を入れており、33.2万人の登録者数(2025年1月31日現在)を保有する人気チャンネルです。
個性的な店員がマニアックな商品を紹介したり、人気作家の1日を追ったりと書店ならではの特性を生かした発信になっています。動画は10分前後のものが多く、空き時間に見るのにちょうどよい長さになっています。販促よりも面白さを重視した内容でファンつくりに成功しています。
谷桃子バレエ団の公式Youtubeチャンネルは、9.9万人の登録者数(2025年1月31日現在)、海外では給料が出るが、日本だと週5日バイトのようなバレエ界の内情についての発信が人気のもとになっています。
最初の1ヶ月での再生回数が320万回と注目され、公演チケットも完売するようになりました。人間心理として物事の裏側を知りたいという点を的確についたのが、注目された要因と考えられます。
2つとも目先の売上を追い求めるのではなく、面白おかしく、知ってもらいたいという姿勢が注目につながったと言えます。
1回のバズリをきっかけに売上アップに成功
島根県にある安本産業株式会社は、「やすもと醤油」のアカウント名でX(旧:ツイッター)を運用している。2020年8月担当者のあるツイートがきっかけでフォロワーは40人から9万人以上と激増。オンラインショップの商品は全て売り切れ、製造も追いつかない状態になりました。
その後も担当者がコツコツと投稿を続け、フォロワー9万人以上はキープし、X上で多くの方との交流を続けています。販促につながるような投稿はなく、自社のことを知ってもらうような投稿で会社への親しみの醸成に成功しています。
商品力がベースになってはいるのですが、コツコツと運用を続けることで一過性のブームに終わらせず、結果として会社の売上アップに成功しています。売上はバズる前の3倍、生産ラインを増設し、社員数も2倍以上に増えています。
バズリの詳細を知りたい方は↓
https://todokel.net/blog/yasumoto-shoyu/
https://www.sanin-chuo.co.jp/articles/-/680954
ある食品メーカーでは、中途入社の広報担当社員がSNSを運用するようになりました。こまめな投稿を継続しながらSNS上で多くのアカウントと交流を深め、会社・商品の認知度アップに成功しました。私自身、交流を通じてこの会社の商品を買うようになり、ファン化が販売につながることを実感しています。
売ろうとすると響かないのがSNSの世界、まずは面白さ、コミュニケーションを深めることが急がば回れで近道になると言えます。
SNSを活用しているが、目的が定まらない。そろそろ本格的にSNSに取り組みたいという会社の方は、会社や商品の認知度や信頼感を上げるという広報の視点を意識して活用してみてはいかがでしょうか?
こちらの記事をご覧の方におすすめ
通販お役立ち資料
無料ダウンロード
タグ:
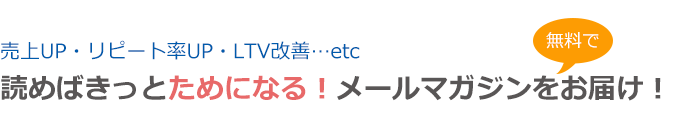
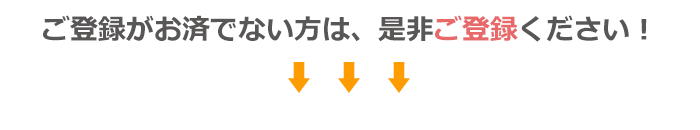

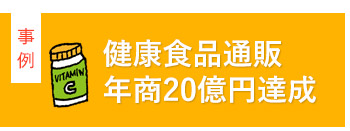
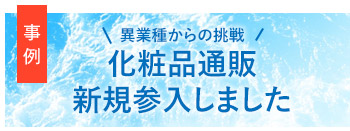
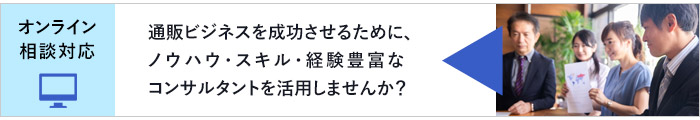
│ EC通販コラムTOPへ │ 通販コンサルTOPへ │